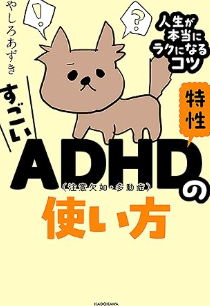落ち着いて座っていたいのに、気がつくと足を揺らしていたり、椅子に座ったまま体をひねっていたり、無意識のうちに席を立ってしまうことがあります。
特に私は仕事を始める最初の段階でこうした症状にかられることがあります。
始めることができれば、集中できるのに最初の導入でこうしたことが頻繁に起きます。
私にとっては自然な行動であっても、周囲からは集中力がない、話を真剣に聞いていないと誤解されてしまうことも学生時代はよくありました。
特に授業中、静かな場所など、動きが目立ってしまう場面では、自分でも抑えようと意識しながら、どうしても体がじっとしていられないことに困惑する瞬間があります。
こうした行動は、単なる落ち着きのなさやマナーの問題ではなく、脳の働き方の特徴によって生じることがあります。
ADHDを持つ人は、脳の覚醒状態や刺激への反応に特有の傾向があり、外部からの刺激や身体の動きを通じて集中を維持しようとする場合があります。
そのため、じっと座っていることが逆にエネルギーを消耗させたり、思考がぼんやりとしてしまったりすることもあるのです。
しかし、この特性は工夫次第で日常生活や仕事への影響を減らすことができます。
無理にじっとしていることだけを目標にするのではなく、体の動きを適切に取り入れながら集中できる環境を整えることがポイントです。
今日は、じっとしていられないという症状を持つ人が、その背景を理解し、自分に合った方法で対処していくための視点と工夫を紹介します。
じっとしていられないのは意志の問題ではない
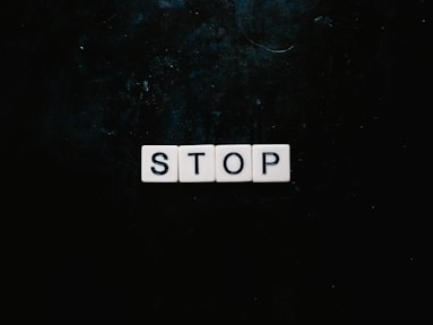
ADHDにおいて、じっとしていられないという行動は単なる癖や意志の弱さから生まれるものではありません。
その背景には脳の情報処理や覚醒状態のコントロールに関する特性が深く関わっています。
ADHDの脳は、外部からの刺激や変化に対して敏感に反応しやすい一方で、刺激が少ない環境では集中を維持しにくい傾向があります。
じっとしていることは、外部刺激を制限する状況になりやすく、脳が求める適度な刺激を得られない状態を作り出してしまうのです。
このとき、身体を動かすことは脳にとって追加の刺激となります。
例えば足を揺らす、手を動かす、姿勢を変えるといった行為は、無意識のうちに脳の覚醒度を引き上げ、思考や注意力を保つための補助的な働きをしています。
つまり、これらの行動は集中を妨げるためではなく、むしろ集中を維持するための自己調整の一部として現れている可能性が高いのです。
さらに、ADHDでは脳内のドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の働きが一般的な人と異なる傾向があると言われています。
これらの物質は注意力や覚醒、やる気に関わっており、その分泌や働きが低下していると、単調な状況や退屈な環境で注意を保つことが難しくなります。
この状態で無理にじっとしていると、集中力が急激に落ち込み、思考が空回りしてしまうこともあります。
また、環境要因も見逃せません。
図書館のように周囲が静かすぎる場所や、刺激が少ない空間では、ADHDの人にとっては集中を保ちにくい環境になります。
逆に、適度な音や動きがある方が、かえって集中できる場合もあります。
あなたも経験があるのではないでしょうか?
図書室の静かな環境よりもスタバのカフェの方が集中できるという事象を。
このように、じっとしていられない行動は環境と脳の特性が組み合わさって生じるものであり、
その背景を理解することは対策を考えるうえで欠かせません。
重要なのは、この行動を単純に抑え込もうとするだけでは逆効果になり得るということです。
本人が持つ集中の仕組みや刺激の必要性を理解し、どうすればその特性を生かしながら周囲との摩擦を減らせるかを考えることが、じっとしていられない症状への根本的なアプローチにつながります。
じっとしていられない人向け|動きをうまく取り入れて集中力を保つ工夫とは?

じっとしていられない特性を持つ場合、まず大切なのは無理に動きを封じ込めるのではなく、動きを生活や仕事の中にうまく組み込むことです。
動きは集中力を支える役割を果たしているため、それを完全に排除してしまうと逆にパフォーマンスが下がってしまう可能性があります。
そこで、周囲の理解を得ながら動きを許容できる環境づくりを進めることが効果的です。
例えば授業のような集団の場面では、席の位置を工夫することが一つの方法です。
後方や端の席を選べば、必要に応じて姿勢を変えたり軽く足を動かしたりしても、周囲への影響を最小限に抑えることができます。
また、仕事をするうえではメモを取る、手元で資料を整理するなど、小さな動作を伴う作業をあえて取り入れることで、身体の動きが集中の維持に繋がりやすくなると言われています。
日常生活では、集中作業の合間に短い休憩を入れ、立ち上がって歩いたり軽くストレッチをする時間を設けてみてください。
この休憩をタイマーやアプリで管理すれば、時間の経過に気づかず動きっぱなしになることも防げます。
特にADHDの特性として時間感覚が曖昧になりやすいことがあるため、外部のツールを活用することは重要です。
また、感覚刺激を満たすための道具を持つことも有効です。
バランスボール、ペン回し、柔らかい触感の小物など、静かに操作できるアイテムは、周囲に迷惑をかけずに動きの欲求を満たす手段になります。
これらは職場や学校での使用にも適していますし、自宅での作業中にも活用できます。
さらに、運動習慣を日常に取り入れることも試してみてください。
ウォーキングや軽い筋トレ、ヨガなど、身体をしっかり動かす時間を持つことで、無意識に体を動かす衝動が和らぐ場合があります。
特に朝や昼の軽い運動は、その後の作業時間の集中力を高める効果が期待できます。
私は仕事に疲れてくると、エルゴメーターのようなものを漕ぐと、比較的スムーズに業務に取り組めるなと感じています。
こうした工夫は、一度にすべてを取り入れる必要はありません。
自分の生活環境や周囲との関係性に合わせ、少しずつ試しながら、自分に合う方法を見つけていくことが大切です。
重要なのは、動いてしまう自分を責めるのではなく、その特性を前提に行動や環境を調整することです。
特性を受け入れつつ適切にコントロールできれば、じっとしていられないことが困りごとではなく、自分の集中を支える力へと変わっていきます。
もしあなたがこうしたことに悩んでいるならぜひ試してみてください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
〇あなたにおすすめの書籍はこちら
変人か? 天才か?
「失くし物」に「うっかりミス」。失敗続き、診断済みの僕が
クセ強凸凹特性と向き合い続けて見つけた、リアルすぎるライフハック集
著者:やしろ あずき/出版社:KADOKAWA